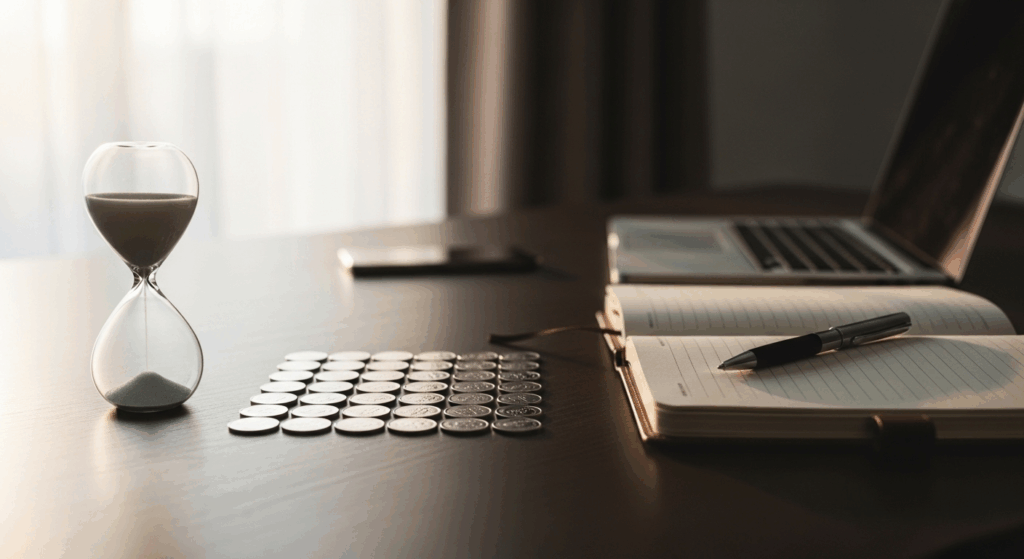
こんにちは、キングスマンです。
今日のアファメーションは「誰もやらないことは私がやる」。これは、僕が年間500万円以上を自己投資に充て、神戸から何度も東京へ通って学んでいた頃に受け取った言葉です。お金も時間も容赦なく出ていきましたが、今になってわかるのは、あの期間が思考の骨格をつくり、日常の決断に芯を通してくれたということ。投じた資源は、いま「語れる」経験として返ってきています。
24枚の硬貨で「時間に予算を組む」
一昨日、子どもとお金の勉強をしました。題材は本に出てきたワークで、タイパ(Time Performance)を“お金”として扱うもの。やり方はシンプルで、1時間=100円に見立て、100円玉を24枚並べるだけです。寝る、学校、ご飯、風呂、通学……と、生活の項目に硬貨を置いていく。宿題を1時間のせたら、残りは4枚。子どもはその4枚を「歌う・ピアノ」に割り当てました。
面白いのは、一度残りが見えてから配分すると、選択が静かに鋭くなること。余白が「見えて」初めて、僕らは捨てる勇気を持てる。タイパの議論は抽象的になりがちですが、硬貨という触れる単位に変換すると、自分の優先順位が指先の動きとして出てきます。大人版の24枚も、同じように効きます。通勤・家事・会議・移動……固定の「時間固定費」をざっと置いていくと、意外と投資に回せる“現金”が少ないことに気づくはず。そこでやっと、何に賭けるかが具体化します。
コツは、24枚すべてを埋めないこと。2~3枚は「突発費」としてあらかじめ残す。これで、想定外の相談やチャンスが来ても、ペースを崩さず差し込めるようになります。時間にもキャッシュポジションが要るのです。
「残るもの」へ時間を寄せる
ぼんやりSNSを眺める時間があってもいい。けれど、ふと立ち止まって「最後に何が残るか」を考える癖は、満足度を確実に上げてくれます。たとえば、形として積み上がる作品や記事、のちの自分を助けるノウハウやチェックリスト、家族の記憶の密度を上げる体験の設計。どれも“残る”方向の時間です。
残ることに時間を寄せると、日々の疲労の意味が変わります。同じ2時間でも、タイムラインに溶けるスクロールと、未来の自分や誰かに届く成果物は、翌朝の自尊心が違う。疲れていても、誇らしい。ここに小さな復元力が生まれます。
「誰もやらない」を仕事に変える——“嫌×平気=価値”の見つけ方
成功している人を観察すると、多くが地味で、誰もやりたがらない作業を長く続けています。突拍子もないことをする必要はありません。大事なのは、自分は嫌じゃないが、他人は面倒に感じる作業を拾えるかどうか。ここに代行の核があります。
たとえば、イベント後の写真整理。何百枚もある写真から使えるものを選び、露出を軽く整え、クラウドで共有し、アルバムの体裁を整える。多くの人は腰が重い作業ですが、これが苦にならない人にとっては価値の塊です。SNS運用の下書き作成・画像差し替え、単発の片付け導線設計、旅行プランの雨天代替、PC/スマホの初期設定と移行チェック——派手さはないけれど、感謝の密度が高い仕事は身の回りにいくつも転がっています。
見つけ方は簡単です。静かな場所で紙を1枚出し、5分で「自分は平気/むしろ好き」な作業を書き出す。次の5分で、周囲の人がよく愚痴る作業を思い出せるだけ挙げる。最後の数分で、交点に当たるものを3つだけ丸で囲む。ここからが実験の始まりです。
試す順番に迷うなら、痛みの大きさ・発生頻度・支払い意欲・自分の負担の小ささをそれぞれ10点満点で直感スコア化し、合計点が高い順に小さく出してみる。1件=30分・無料のテストから始めて、成果物の雛形を作る。作業前後のスクショ、チェックリスト、納品形式(たとえば「Googleフォトの共有アルバム+サマリー1枚」)をテンプレート化できたら、すでに半歩プロダクトです。
価格は最初から完璧に決める必要はありません。3回の実験で、時間あたり単価と提供範囲の境界が見えてきます。境界が見えたら、“ここまでは基本料金・ここからは追加”を言語化し、短い文章で相手に渡す。プロの雰囲気は、曖昧さを減らす説明から立ち上がります。
期限に強くなる——同じ行動でも“差額”が生まれる
「誰もやらないこと」は、派手な発想ではなく、締切に淡々と間に合わせる地味な行動であることが多い。ふるさと納税やポイント施策のように、制度やキャンペーンのルールが動く領域では特にそうです。日付が1日ズレるだけで付与や特典が変わることがある。つまり、決断と行動の早さそのものが可視の差額になる。
僕自身、早めに動いたことで数千〜1万ポイント規模の差が生まれた経験が何度もあります。これは、働いて稼いだというより、判断のタイミングで拾った収益です。もちろん制度やキャンペーンは変更されます。だからこそ、自分のカレンダー側に仕組みを置く。毎月・毎週の「チェック日」を決め、情報の元(公式)を短時間で確認→即断できる導線を用意する。
数式は簡単です。
差額 =(特典率の差)×(支払い額)。
加えて、“先に終わる”ことで空く時間も差額だと考える。時間の早期回収は、次の挑戦の着手が前倒しになるからです。
“AI × 代行”で探索スピードを上げる
AIは疲れず、ジャッジせず、調べて返してくれる壁打ち相手です。代行アイデアの初期探索や、提供フローの安全運転の確認に相性がいい。大仰なプロンプトは要りません。以下の三行を状況に合わせて埋めるだけで、具体案が一気に出てきます。
① 目的:私が「嫌じゃない×他人は嫌」の代行候補を3つ抽出したい
② 現状:候補は□□□。想定顧客は△△。不明点は××
③ 制約:準備は今週2時間/コスト0〜5,000円/1件30分以内
返ってきた案を読んだら、その場で差分指示を入れていく。「この工程は自分の強みではないから別のやり方で」「納品形式は家族・高齢者が使える形に」など、ユーザー像を具体にすればするほど、アウトプットは使える案に近づきます。
旅行計画にAIを連れていく——ケース:ディズニー
我が家は3月にディズニーへ行く予定です。チケット発売タイミングが近づくと、情報は一気に複雑になります。トイ・ストーリー・マニア!を3回乗るならどうするか、ミラコスタに泊まるならどんな動線が良いか、合計いくらかかるのか。この手の検討を、検索とリンク巡回だけでやると、途中で疲れてしまう。
そこで、前提・希望・制約・予算の幅をAIに渡して、複数の代替案を出してもらう。たとえば「朝の到着時刻が30分遅れたときの再計画」まで提案してもらえば、現地の意思決定は驚くほど軽くなります。大事なのは、“完璧な正解”を探すのではなく、意思決定の準備を前倒しすること。旅行は「現地で迷わない」ことが最大の快適さです。
今日の学びを、明日の設計に接続する
時間に予算を組み、残る方向に寄せ、誰もやらない地味な作業を静かに拾う。そして期限に強くなる。これらは別々の話ではありません。どれも、今日の意思決定を明日に効かせる技術です。
24枚の硬貨は、あなたの現実を映す鏡です。全部はできないという事実を、やさしく受け止めさせてくれる。そこから、3つだけ賭けどころを選ぶ。代行の実験は、誰かの「面倒」を、自分の「平気」で包むこと。最初の3件が終わったら、あなたの中に再現可能な小さな仕組みが残ります。
そして、締切。これは、焦るためのものではなく、差額を拾うためのレールです。行動のタイミングが変わるだけで、数字も、心も、驚くほど変わる。
P.S.
学びに投じたお金と時間は、かならず体験として戻ってきます。「誰もやらないことは私がやる」。今日も愚直に、一個ずつ。あなたの24枚のうち、たった1枚でいい。明日に残る何かへ、静かに置いてみてください。